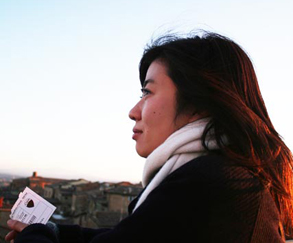#4「最初は変な宗教かと思った」

周りには花が咲き、遠くから虫の声が響いている。
夕暮れの時の「夢の家」は、前回よりも美しく見えた。ああ、再びここに来られて嬉しいなあと胸を高鳴らせながら、「こんにちは、お邪魔します」と家に入った。
中では、「夢の家」の管理人さんを務める恵美子さん(57歳)、幸子さん(69歳)、雅子さん(70歳)が待っていてくれた。三人は、農業などの仕事をしながら、もう15年間もこの家を守っている。
さて、集落とアートの出会いとは、一体どのようなものだっただろうか。
幸子さんが、初めて「夢の家」の構想を聞いたのは、部落の集会の時だったそうだ。
「あの時は、『なんだ!?』と思いました。気持ち悪いというか、感じが悪いというか。最初は、変な宗教かと思いましたね」
その集会の記録映像を見てみると、年配の男性が棺桶形のベッドを指して、「これは寝心地が悪いのではないか」というような指摘をして、マリーナが「もちろん、わざわざ寝心地が悪く作っています。夢を見るために」と英語で答えているのが映っている。
そんなチグハグなやり取りのせいか、集落の人たちは、「なんであんなものを作るのだろうか。まあ、なるべく寄り付かないでいよう」という半ば無関心を決め込こんでいた。
家の改修に大活躍したのは、都会の学生を中心とした芸術祭ボランティア、「こへび隊」だった。若者たちは精力的に働いて、この家に長年溜まっていたゴミ(実にトラック8台分!)を運び出し、廃屋寸前の家をアート作品に生まれ変わらせた。その頑張っている姿には集落の人もすっかり胸を打たれ、昼食やお茶をせっせと運んだそうだ。
外国から来たアーティスト、学生ボランティア、集落の住民、という立場も背景も全く異にする三者が一緒に汗を流すことで、夢の家は産声をあげた。
そして、迎えた芸術祭の第一回目。長年静かだった集落に、何かが起こるぞという予感が溢れていた。
蓋を開けてみると、夢の家にはなんと71名もの宿泊者がやってきた。それまで来客など皆無の集落にとって、これは大変な驚きだったようだ。こんな田舎まで? あんな奇妙な古民家に泊まりに!?
やがて「夢の家」は、雑誌やテレビで取り上げられ、訪問客は徐々に増加。第二回目(2003年)には、宿泊客は300人、日中の訪問者は一万人に迫った。
そうしていくうち、いつしか集落の人の態度も変わっていった。
「(お客さんたちは)、Gパンが穴だらけとか、下着を出して服を着てるとかで、最初は村の人たちは、『あ、夢の家に泊まる人だ』って感じで遠くから見てました。でも、挨拶してくれる人もいるし、話すとみんないい人ばっかりで。悪い人はいなかったですねえ。私は、芸術はいまだによくわからないけどねえ、十何年ここに関わってきて、だんだん(自分も)村の人も受け入れられるようになってきた」(雅子さん)
「夢の家にたくさん人が来るようになって、みんな喜んで帰ってくれます。それが嬉しいですね。現代アートそのものは、私たちはあんまり興味がないですけど、いつの間にか、『夢の家』に私たちも“想い”を持つようになったのは事実ですね」(恵美子さん)
そうして、集落の人は周りに花を植えたり、菜園を作ったりするようになり、取り巻く雰囲気もだいぶ変わっていった。そうして、この15年間で、夢の家は、すでに二千五百人以上のドリーマーを迎えいれている。