#3学校はカラッポにならない

「夢の家」のチェックインは夕方五時と決まっているので、私たちは、飛田さんが薦める廃校を利用した「鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館」に立ち寄ることにした。芸術祭自体は三年に一度だが、その他の時期でも数え切れないほどの常設作品を見ることができ、ここも、そのひとつだ。
玄関を入って懐かしい雰囲気の下駄箱に靴を入れると、かつての体育館が見えた。その時、「絵本の原画でも展示しているのかな」という予想は、全く的外れだったことに気づいた。
体育館には、カラフルな流木でできた巨大なオブジェのようなものが、空間いっぱいに吊り下がっている。よく見ると、人の形をしたそのオブジェはゆらゆらと動いていて、元気いっぱいに飛び跳ねているように見えた。その独特の躍動感に圧倒されながら、私は「何なんですか、ここは!?」と尋ねた。
先のNPOでこの美術館の運営を担当する天野季子さんは、「ここのコンセプトは『空間絵本』なんです」と解説する。作品を作ったのは、『ちからたろう』などで有名な絵本作家の田島征三さん。
「最初は、田島さんの絵本作品を展示することを考えていたのですが、提案があったのは『学校はカラッポにならない』というこの学校と生徒を舞台にした物語でした。(2005年に)学校が廃校になった時、ユウキ、ケンタ、ユカの三人の生徒がいたんですが、その子たちはみんな転校していきました。でも、子ども達は、きっとここで卒業したかったのではないでしょうか。だからこの作品には、学校の記憶が込められているのです」
物語は、転校した三人が、大切にしていた菜園を見にくる、というところから始まる。すると、学校には「トペラトト」という思い出を食べるオバケが住んでいる。
そうして、学校全体を使って一つの物語が紡がれていく。見ている方も色々な形で参加することができ、いつしか三人の子どもやトペラトトと遊んでいるような気持ちになっていく。
「こりゃ、楽しいですね!」と私はワクワクしながら校舎を巡った。その後はHachi Café という美術館の中にあるカフェで、飛田さん、天野さんとランチを食べた。
「地元の人にとって廃校というのは本当に悲しいものなのです」
と飛田さんはいう。廃校は、自分の思い出の学校がなくなるだけではない。この先、子どもが集落から去り、過疎高齢化がますます進み、周辺が寂しくなることを意味する。
しかし、この美術館ができた後は、日々、観光客や地元のお母さんたちが子どもを連れて遊びにくるようになった。そうやって、誰かが遊びに来れば、学校には新たな思い出が刻まれ、この先もカラッポにならない————。
素敵なコンセプトの美術館だなあと思った。
その後も私たちは高台から素晴らしい棚田が見渡せる星峠や、沿道にある作品を巡りながら、いよいよ「夢の家」に向かった。
-
 星峠の棚田。この土地の人々は、この棚田の風景を守ってきた。
星峠の棚田。この土地の人々は、この棚田の風景を守ってきた。 -
 かささぎたちの家(金九漢 キム・クーハン)は、中に入ることもできる。
かささぎたちの家(金九漢 キム・クーハン)は、中に入ることもできる。
未知の細道 No.71
未知の細道の旅に出かけよう!
こんな旅プランはいかが?
二泊三日
新潟・越後妻有

- 1日目
- 越後妻有里山現代美術館キナーレにて展示を鑑賞。
その後、 明石の湯 で一風呂。夕方、 夢の家 にチェックインし一泊。 - 2日目
- 絵本と木の実の美術館 森の学校キョロロ その他の沿道にあるアート作品をめぐってドライブ。夜はお好きな「泊まれるアート施設」 に宿泊。
- 3日目
- 星峠や棚田やブナ林 「美人林」 など、里山の風景や自然を満喫してリラックス。
※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。
最新の記事
- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25
- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10
- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25
同じライターの他の記事
- 美咲芸術世界が織りなすヘンテコな世界〜パリから棚田に舞い降りた常識ハズレの風雲児たち〜2018.9.10
- 高円寺に出現した謎の巨大壁画を探せ!街の“予定調和”を崩すアート2018.8.10
- わたしたちは誰もが芸術家なのか?「黒板消し」から始まった小さな美術館がいま伝えたいこと「カスヤの森現代美術館」2018.5.10
人気の記事
- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10
- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25
- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25
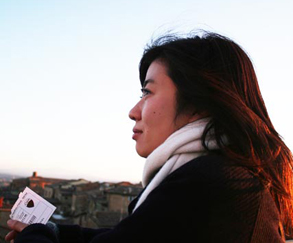
川内 有緒
コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。「空をゆく巨人」で第16回開高健ノンフィクション賞受賞。
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。


