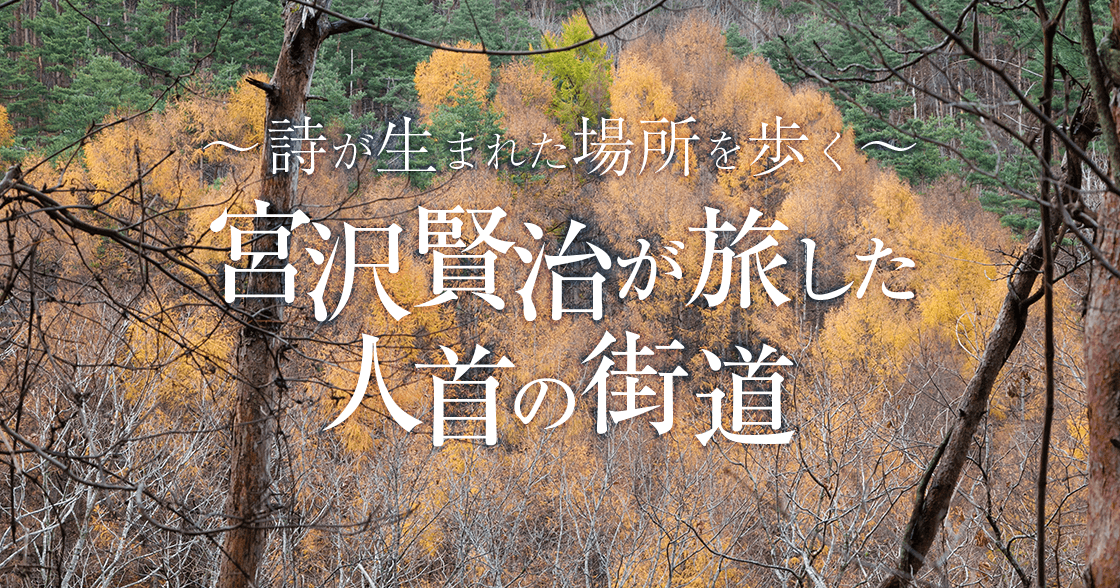#4静かなる五輪峠

山の天気は変わりやすい。人首の町には、また戻ってくることにして、天気がいい午前中のうちに、五輪峠まで車で登ってみることにした。かつて人や馬が歩いて通った五輪峠への道はすでに使われなくなり、昭和31年(1956)になって新しい道路ができている。時代と共に全く使われなくなった旧道は大半が草木に埋もれてしまったが、そのおかげで賢治たちが歩いた当時のままの道が残った。近年その一部を佐伯さんたち「賢治街道を歩く会」が整備して、昔の峠道の雰囲気を歩いて体感できるようになっているのだ。
佐伯さんは「昔は水沢から人首を通ってこの峠を越えて遠野や、さらに宮古などの三陸海岸まで出たんですよ」と教えてくれた。賢治も行った遠野だが、昔はこの峠が人首から遠野に出る唯一の道だったのだ。

五輪峠の頂上まで行くと、名前の由来となっている「五輪塔」がある。
この付近の武士が先祖の供養のために350年ほど前に建てたもので、すでに2度ほど代替わりしているらしい。賢治が見た塔は2代目だろうと言われている。
「五輪峠」という詩の中にはこう書かれている。
あゝこゝは
五輪の塔があるために
五輪峠といふんだな
ぼくはまた
峠がみんなで五っつあって
地輪峠水輪峠空輪峠といふのだらうと
たったいままで思ってゐた
地図ももたずに来たからな
『新校本宮澤賢治全集』(筑摩書房、2009)より引用

実は五輪峠には戦にまつわる言い伝えなどが多く、平成に入ってからも、摩訶不思議なことが起こると言われている場所なのだそうだ。行く前から佐伯さんにさまざまな言い伝えを聞いていたので、なんとなくドキドキしながら五輪塔の周りを歩いた。
賢治は1度目の旅では、五輪垰で野宿したのだが、のちにその夜のことを「とても恐ろしさを感じた、その静けさは死と同様である」と恩師に語っている。賢治の文学は、大いなる自然との交感が豊かに描かれているのも魅力の一つだ。そんな賢治だからこそ、この地にヒヤリとする何かを感じ取ったのかもしれない。音楽家の友達もあたりに耳を傾けながら、確かにここは音がないなあ、静かすぎる、と呟いていた。
峠を下って人首へと向かう行く道すがら、蛇紋岩という、鉱物を多く含んだ火成岩の露頭が目につく。子供の頃から「石コ賢さん」と呼ばれるほど鉱物採集に熱中し、長じてからは地質を学んだ賢治だが、学生の時の旅も地質調査が目的だった。以後の作品のモチーフにも、地質や鉱物は深く関わってくる。
1度目の旅では蛇紋岩をハンマーで割りながら「ホーホー20万年もの間日の目を見ずに居たのでみんな驚いている」と叫んだ、と同行した友人の逸話が残っている。もしかしたら、この蛇紋岩のどこかに賢治がハンマーをあてたのかもしれないな、と思えば、自分にとってはなんでもないはずの岩でも、急に違って見えてくるから不思議だ。蛇紋岩を含め、この辺り一帯の地盤は太古の昔は海の底にあったものだ。自然の神秘が賢治の心を刺激したことは間違いなさそうだ。

未知の細道 No.104
未知の細道の旅に出かけよう!
こんな旅プランはいかが?
人首の歴史&近代文学史をめぐる旅プラン 2泊3日
予算の目安2万5千円〜

- 0日目
- 人首周辺がモチーフになっていると言われている宮沢賢治の詩や物語を事前に読んで、その世界観を予習。
- 1日目
- いよいよ人首の町へ。まずは「五輪峠・賢治マップ」と「人首・賢治マップ」(賢治街道を歩く会発行)を片手に、宮沢賢治が歩いたメインストリート、旧菊慶旅館、神社、田んぼのあぜ道、人首川などのゆかりの場所を巡る。さらに「人首文庫」で詩人・佐伯郁朗が集めた、萩原朔太郎や、中原中也などの詩人たちの貴重な資料も見てみよう。(入館無料、要事前予約。電話0197-38-2137)
- 2日目
-
午前中は五輪峠と五輪街道へ。(冬季は通行止の道もあるので注意。)
午後は、盛街道を通って、分教場跡、栗木鉱山跡、種山高原を巡る。
道の駅「種山ケ原」にも、宮沢賢治の詩碑があるので立ち寄ってみよう。 - 3日目
- 大森山にある人首丸墓碑など、蝦夷一族ゆかりの地を巡る。
※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。
最新の記事
- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25
- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10
- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25
同じライターの他の記事
- めざせ!日本一のサイクリングの街・土浦 路地裏から湖までを巡る自転車の旅2018.10.10
- 今も昔も女の子をときめかせる美しき雛人形「桂雛」の世界2018.9.25
- 77万年前の地磁気逆転地層を目指して!養老川と地層を巡る2018.7.10
人気の記事
- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10
- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25
- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

松本美枝子
主な受賞に第15回「写真ひとつぼ展」入選、第6回「新風舎・平間至写真賞大賞」受賞。
主な展覧会に、2006年「クリテリオム68 松本美枝子」(水戸芸術館)、2009年「手で創る 森英恵と若いアーティストたち」(表参道ハナヱ・モリビル)、2010年「ヨコハマフォトフェスティバル」(横浜赤レンガ倉庫)、2013年「影像2013」(世田谷美術館市民ギャラリー)、2014年中房総国際芸術祭「いちはら×アートミックス」(千葉県)、「原点を、永遠に。」(東京都写真美術館)など。
最新刊に鳥取藝住祭2014公式写真集『船と船の間を歩く』(鳥取県)、その他主な書籍に写真詩集『生きる』(共著・谷川俊太郎、ナナロク社)、写真集『生あたたかい言葉で』(新風舎)がある。
パブリックコレクション:清里フォトアートミュージアム
作家ウェブサイト:www.miekomatsumoto.com
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。