#2伝統を継ぐ「桂雛」

ある夜のこと。20時くらいだっただろうか。私は友人のくみちゃんと夜の街を歩いていた。するとくみちゃんが突然、もう閉館したギャラリーのショーウィンドウの前で立ち止まって「これを見たい!」と言いだした。中を覗くと、漆塗りや木工などのさまざまな伝統工芸品が並んでいる。
さらにその奥に、ひときわ美しい雛人形が見えた。どうやらくみちゃんは、その人形をどうしても間近で見たくなってしまったらしい。某有名化粧品ブランドに勤め、とある百貨店の1階で美容の仕事をしている彼女は、きれいなもの、かわいらしいものに目がないのだ。
閉館したギャラリーでは展示品の搬出作業が始まっていたところだったのだが、扉が開いているので、思い切って「見せてもらえませんか」と声をかけてみた。すると一人の男性が快く応じてくれ、この雛人形のつくりを丁寧に説明してくれた。
その人こそがこの雛人形を作った人形作家、小佐畑孝雄(こさはたたかお)さんだったのだ。人形の顔立ちや所作も、そして伝統的な十二単のなかに垣間見えるモダンで斬新な色使いもさることながら、それにすっかり心を奪われている様子のくみちゃんを見て私は思った。
私はこれまで雛人形とは、自分の日常からは少し遠い、高価な「伝統工芸品」だとしか考えていなかった。でも目をキラキラさせて美しい雛人形を見ている友人を見ていたら、雛人形の持つ輝きは、これまで何百年も日本の女の子たちの心をつかんできただけあって、もしかしたら、すごい力なのかもしれないなあ、とふと思ったのだ。 そんな雛人形は一体どうやって、この世に生み出されているのだろうか? 優しそうな小佐畑さんの雰囲気にも、ますます興味がわいた。そしてその場で「ぜひ工房を見学させてください」とお願いしたのであった。
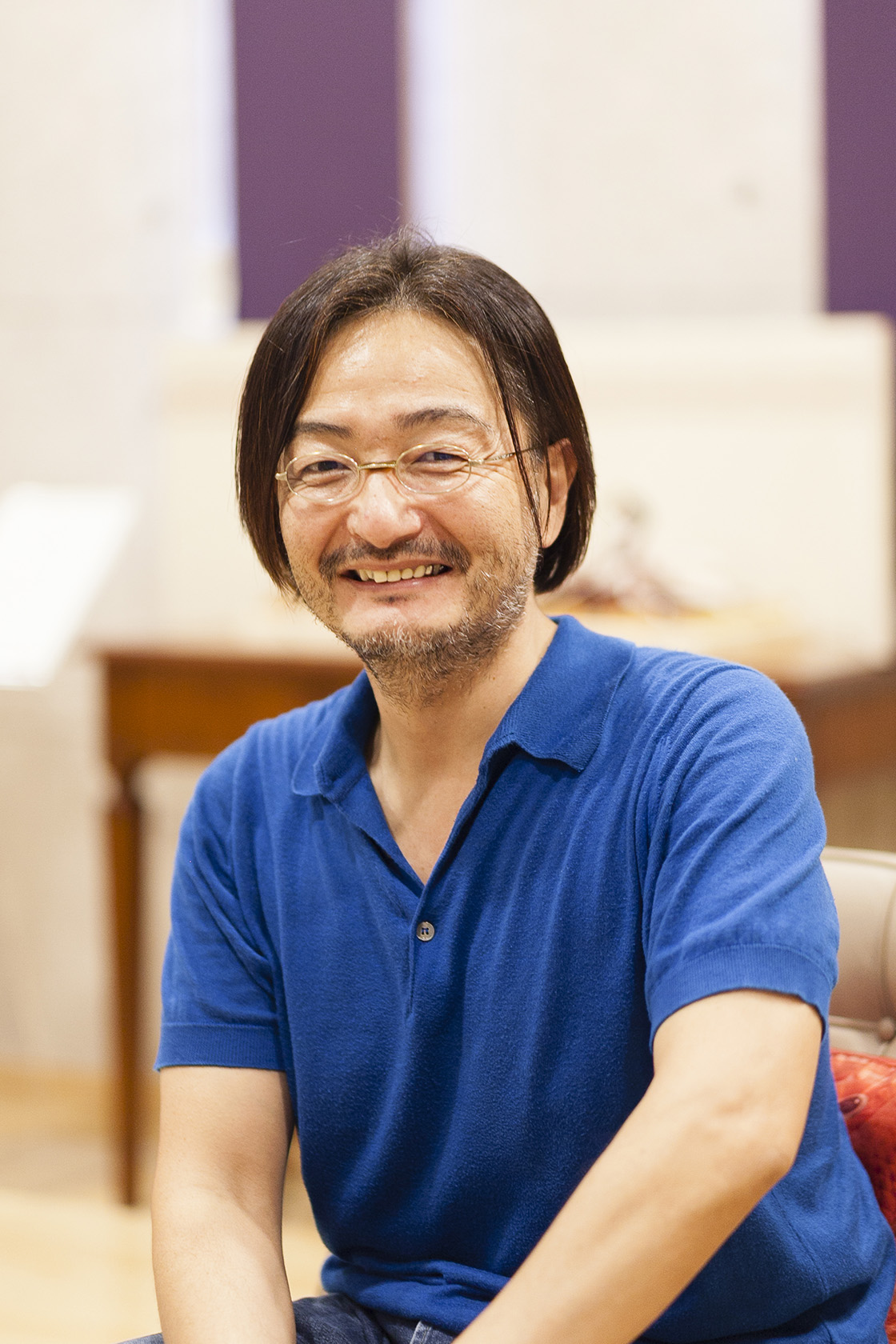
こうしてやってきた城里町桂地区の「小佐畑人形店」。もちろん、くみちゃんもいっしょだ。出迎えてくれた小佐畑さんは、さっそくこの土地と桂雛の歴史を語ってくれた。
城里町から20キロほど離れた茨城県水戸は、かつては雛人形の町としても栄えていた。「水府雛」である。(水府は水戸の古称)。昭和40年代までは日本で3本の指に入るほどの大きな問屋もあったという。だが今では水府雛の作り手は一軒しかない。人々の生活スタイルが大きく変わったことにより、伝統工芸の多くがいわゆる「衰退産業」となってしまい、雛人形づくりもその一つであるからだ。
小佐畑さんの祖父は、もともとその「水府雛」の職人だった。独立して、どこに店を構えようか、ということになった時に思い浮かんだのが、水戸からもそう遠くない「関東の嵐山」、旧桂村だったのだ。
「祖父は真面目な昔堅気の職人だったので、宮中ゆかりの雛人形の流れを守ることを大切に考えていたのでしょうね」風光明媚で、かつ古くから都の伝説が残る桂村は、雛人形作りにはぴったりの雰囲気の土地柄だったのだ。
こうして1930年(昭和5年)ごろから、桂村での小佐畑家による雛人形作りが始まった。これが雛人形の産地「桂雛」の始まりである。こうして江戸時代から続いてきた「水府雛」の系譜が、少し離れた山あいの町に、今でも「桂雛」として根付いているのである。

未知の細道 No.122
未知の細道の旅に出かけよう!
こんな旅プランはいかが?
美しき雛人形「桂雛」の世界を巡る旅プラン(日帰り)
予算の目安10,000円〜

-
城里町桂地区へ。
まずは小佐畑人形店へ。ショールームで美しい「桂雛」を見てみよう!
つづいて「関東の嵐山」と呼ばれる風景を散策。御前山ではハイキング、那珂川ではキャンプやカヌーなども体験できる。周辺には日帰り温泉などもある。
城里町は今秘かなカフェブーム!いくつか新しいカフェができている。那珂川の眺望が抜群のMERCY'S COFFEEなど、巡ってみてはいかが。
※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。
最新の記事
- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25
- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10
- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25
同じライターの他の記事
- めざせ!日本一のサイクリングの街・土浦 路地裏から湖までを巡る自転車の旅2018.10.10
- 今も昔も女の子をときめかせる美しき雛人形「桂雛」の世界2018.9.25
- 77万年前の地磁気逆転地層を目指して!養老川と地層を巡る2018.7.10
人気の記事
- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10
- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25
- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

松本美枝子
主な受賞に第15回「写真ひとつぼ展」入選、第6回「新風舎・平間至写真賞大賞」受賞。
主な展覧会に、2006年「クリテリオム68 松本美枝子」(水戸芸術館)、2009年「手で創る 森英恵と若いアーティストたち」(表参道ハナヱ・モリビル)、2010年「ヨコハマフォトフェスティバル」(横浜赤レンガ倉庫)、2013年「影像2013」(世田谷美術館市民ギャラリー)、2014年中房総国際芸術祭「いちはら×アートミックス」(千葉県)、「原点を、永遠に。」(東京都写真美術館)など。
最新刊に鳥取藝住祭2014公式写真集『船と船の間を歩く』(鳥取県)、その他主な書籍に写真詩集『生きる』(共著・谷川俊太郎、ナナロク社)、写真集『生あたたかい言葉で』(新風舎)がある。
パブリックコレクション:清里フォトアートミュージアム
作家ウェブサイト:www.miekomatsumoto.com
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。


