
写真家ユージン・スミスが日立にいた2年間と、その道のりを探った20年
写真= 松本美枝子、山野井咲里(#6のみ)
未知の細道 No.183 |12 April 2021
#8日立と日本を映し出す鏡

ユージン・スミスという写真史に残る写真家が日立の街で撮影した事実は、大森さんが学芸員という職業に就くきっかけとなり、その後20年近く、その調査に没頭することになった。
大森さんにとって、ユージン・スミスとは、いったいどんな存在なのだろうか? 聞いてみた。すると大森さんは、少し考えながら、こういった。
「出会うべきときに出会えた、がっちり心を掴まれた、比類なき存在ですね」
そして「スミスの写真は、日立を映し出す鏡であり、日立にとってかけがえのない財産になった」と大森さんは続けた。
ではユージン・スミスにとって「日立」とは、いったいどんな存在だったのだろうか。それにはこんな答えが返ってきた。
「おそらくスミスは日本が好きだったんだと思います。日立で自分の撮影アシスタントを務めてくれた三人の日本人たちに、スミスは笑って『自分の体には沖縄戦の砲弾が埋め込まれている』と語っていたそうです。そんな、おそらく最初は憎むべき敵だった日本を、沖縄、日立、水俣と日本をおよそ10数年ごとに活写するうちに、日本が好きになっていった」
日立は、きっとその魅力に最初に気づいた場所だったのだろう。
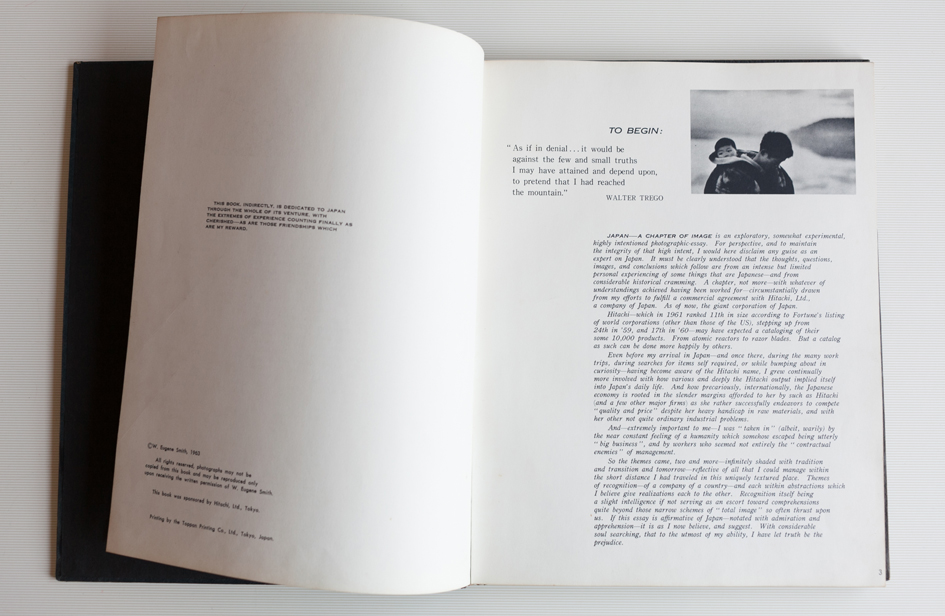
その思いは『Japan ... a chapter of image』の1ページ目に込められている、と大森さんは言う。日立市の久慈浜という海岸で撮られた子どもの写真だ。
本来は大企業のPR写真を撮りに来たはずなのに、会社とも工場とも関係ない、市井の子ども、それも日本の高度経済成長から完全に取り残されているような、寂しげな漁村の子どもを捉えている。
世界的企業を目指して前進するクライアントの依頼など、すっかり忘れたかのようなこの1枚を、写真集の1ページ目に据えたスミスの視点、そのヒューマニズムは、やがて水俣での大仕事につながっていく、と大森さんは言う。
日立の漁村・久慈浜を見たスミスはその数年後、「また日本の漁村を撮りたい」と言っていたそうだ。

そして「山間の大きな工場も、そのすぐそばにあった高度経済成長から取り残されたような漁村も、実は日立と水俣の風景は相似をなす」と大森さんは指摘する。日立での経験は、その後のスミスの水俣行きに何らかの影響を与えただろう、と研究者の間でも言われている。
日立での撮影から10年後、スミスは導かれたように水俣の撮影へとのめり込んでいく。水俣病患者や新聞記者たちへの強制排除のなかで起こった暴行事件に巻き込まれ、片目失明と脊椎骨折という、沖縄戦で受けた以上の大きな傷を負いながら。そしてその傑作は、日本の高度経済成長の裏で起きた悲惨な公害を世界へ発信するきっかけとなった。
日立のみならず、20世紀の日本の節目節目を映し出す鏡だったとも言えるスミスの写真。そして大学生の時にその写真を知って以来、今、50歳になった大森さん。大森さんは、スミスのオリジナルプリントを収蔵するワンチャンスを、まだ狙っているのだ、と静かにいう。芸術の世界では「神は細部に宿る」とよく言われるが、写真家の本質を知るには、やはりそのオリジナルプリントに勝るものはないからだ。
それが実現したらいいな、と思う。根拠はないけれど、いつかきっと日立にスミスのオリジナルプリントがやってくる日が、くるような気がしている。写真という文化を通して、社会を真摯に見つめていこう、と考える研究者たちがこの街にいる限り。
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。










