#4街が家になるという不思議感覚

「そもそも僕は、“街全体が家だ!”っていう感覚を持っていた」
と大黒さんはバーのカウンターで語り始めた。
ん? それはいったいどういう感覚なのだろう。確かに高円寺には、活気のある商店街も、銭湯も古着屋も飲み屋もギュッと詰まっているわけだけど、彼が言いたいのはそういうことだけでもなさそうだ。
「まだ二十代のときですが、実は、8ヶ月間、“家なし”で暮らしていたことがあるんですよ」
えっ!? 家なし生活?
よく聞いてみると、家を追い出された、とか家賃が払えなかった、というわけではなく、自ら選んで家具などを処分し、借りていたアパートを出たと言う。そして、高円寺の街の知り合いの家を転々としながら、身ひとつで暮らし続けた。
「家とか部屋って、けっこう空いてたりすんですよ。子どもが独立しちゃって、子ども部屋が空いてるという話も多い。そんな街の隙間を狙って暮らしてけるんじゃないかなって」
それは、彼なりの人生の実験だったという。そこで立てた「問い」は、人は街全体を家として暮らしていけるのか? というもの。ルールはとにかく誰にも家賃を払わないこと。そのルールを守りながら、友人の実家や夫婦のマンションの一室を転々とした。家賃は払わない代わり、皿洗いや掃除を手伝った。
「飲みの誘いを断らないっていうルールもありました。そうしたら、ある家では(お酒を)毎日のように飲むので、実はすごい大変でした!」
そうやって、高円寺で暮らした8ヶ月は、“街全体が自分の家になる”という独特の感覚を生み出したという。その後ごく自然に、空き家や、オーナーが夜逃げして空いてしまったバーなど、都会の小さな「隙間」を狙って、アート作品の展示をしたり、イベントスペースを作るようになった。
それにしても、あえて「家を持たない暮らし」をするならば、旅に出るという選択肢もあっただろう。なぜあえて「高円寺」というホームタウンに留まり続けたのだろうか。
「旅に対する憧れがあったんだけど、その時はお店(オルタナティブスペースのAMPcafe)をやっていたので、なかなか旅に出られなくて。でも日々の生活をマンネリ化させずに、新しい一日をエンジョイできないかと考えて、あえて住処を変えるということをやってみた。だから、もう旅のように毎日楽しく暮らしていましたよ」
そうやって高円寺というカオスな街に深く入り込んでいた大黒さんは、ある日、「高円寺でホテルを立ち上げたい」という建築家や事業家など若者3人のグループに出会った。そのチームに不足していたのは、高円寺のコミュニティのことをよく知るアートディレクターだった。それは、まさに大黒さんという存在そのもの。
「僕の考えや思いと彼らの必要とするものがマッチして、出会ってすぐにホテルというよりも、“体験型のアートルーム”を作ろうということになりました」
そうして、他の3人も高円寺に引っ越してきて、「動物園」の仲間入りを果たしたのだ。
未知の細道 No.119
未知の細道の旅に出かけよう!
こんな旅プランはいかが?
高円寺の巨大壁画を巡る旅プラン
予算の目安30,000円〜

- 1日目
- 壁画巡りをしたり、ライブハウスを巡ったり、古着を買ったり。ローカルでディープな高円寺を存分に楽しむ。伊東豊雄さん設計の劇場「座・高円寺」で観劇なんかもいいかも。地元の人が集まる飲み屋さんやバーで街の人と知り合うのも楽しみのひとつ。夜はBnAホテルに宿泊して、その作品世界のどっぷり浸かってみては?
- 2日目
- 同じく個人店が軒を連ねる人気急上昇の西荻窪を訪ね、ローカルな古本屋や隠れ家カフェをめぐり、自由に散歩。善福寺公園や井の頭公園まで足を伸ばすのも楽しそう。もっとアクティブな人ならば、中央線に乗ってビューンと高尾山まで行ってしまうのもアリ。
※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。
最新の記事
- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25
- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10
- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25
同じライターの他の記事
- 美咲芸術世界が織りなすヘンテコな世界〜パリから棚田に舞い降りた常識ハズレの風雲児たち〜2018.9.10
- 高円寺に出現した謎の巨大壁画を探せ!街の“予定調和”を崩すアート2018.8.10
- わたしたちは誰もが芸術家なのか?「黒板消し」から始まった小さな美術館がいま伝えたいこと「カスヤの森現代美術館」2018.5.10
人気の記事
- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10
- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25
- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25
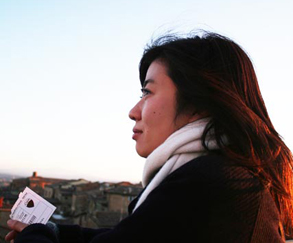
川内 有緒
コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。「空をゆく巨人」で第16回開高健ノンフィクション賞受賞。
未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。


