#6年縞は世界のものさし
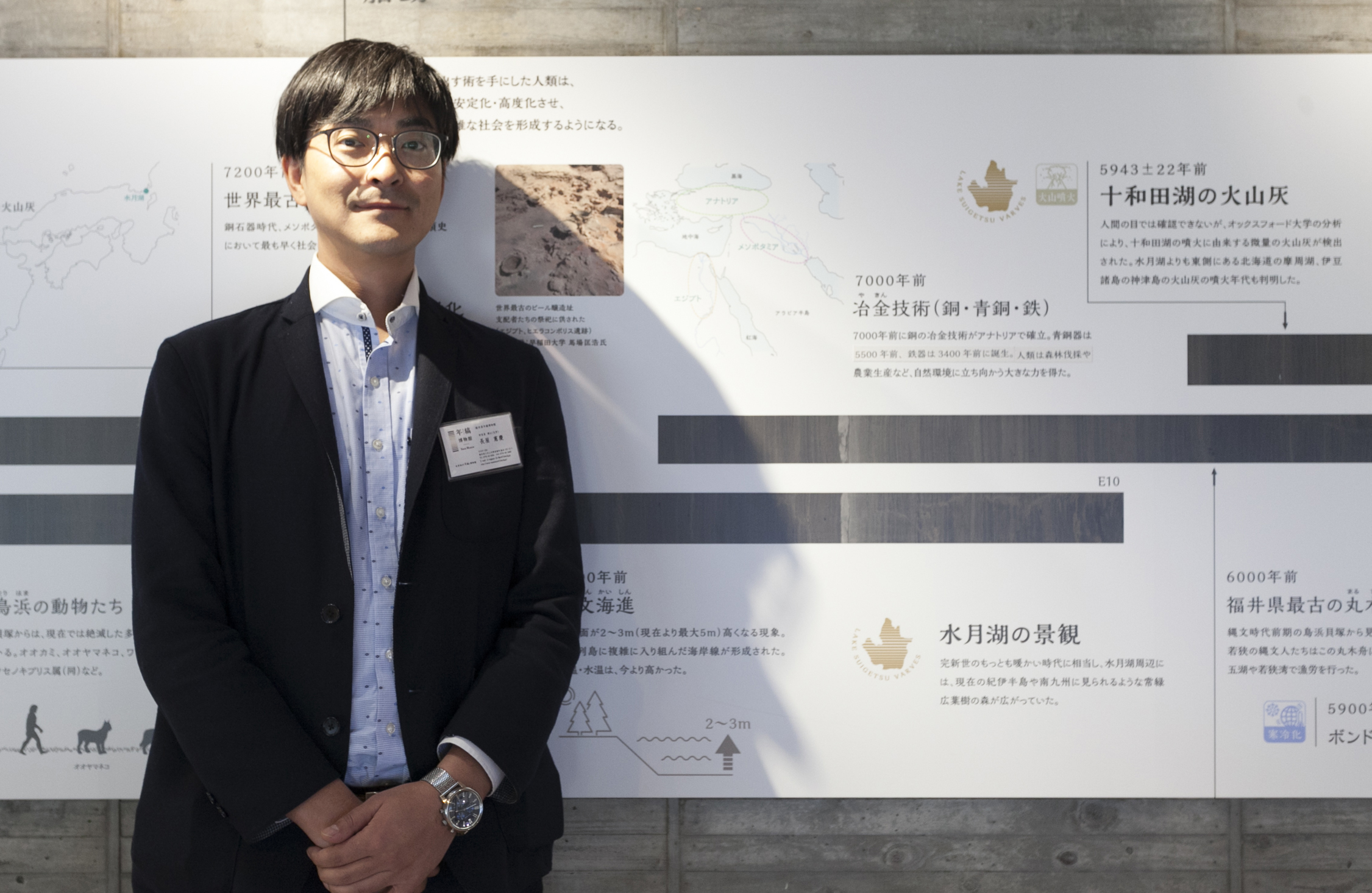
さて水月湖の年縞は「世界標準のものさし」と呼ばれている。これがどういう意味なのか、年縞博物館の学芸員、長屋憲慶(ながやかずよし)さんが教えてくれた。
長屋さんの専門は、なんとエジプトの考古学。この博物館は自然科学の学芸員で構成されていると勝手に思い込んでいた私は、長屋さんが文系の学芸員だと聞いて少々びっくりした。しかしこれにも、もちろん年縞が関係しているのだという。

地質学でも考古学でも、化石や遺跡などの年代を調べるためには放射性炭素年代測定という方法が使われている。この測定方法は動植物に含まれる放射性炭素(炭素14)という物質を利用している。しかし放射性炭素の量は年代によって変動し、一定ではないため、この方法は必ずしも正確であるとは限らない。この誤差を埋めるためには国際的な合意に基づいて統一された「較正モデル」(較正とは比べて正す、という意味。キャリブレーション)という換算表が必要だという。
一方、水月湖の年縞は途切れなく堆積しているため、縞の数を数えればいつの年のものかほぼ特定できるし、さらに年縞に含まれる葉の化石の炭素14を測定することでその年代の炭素を正確に測定することができるようになった。これによって世界中で測られた放射性炭素年代は水月湖のデータと対比することで、水月湖の何枚目の縞に含まれた葉の化石に相当し、いつの年代のものなのか? ということが詳しくわかるようになったのだという。
さて現在、世界で最も広く使われている較正モデルは「IntCal」と呼ばれ、数度の更新を経て精度を高めてきた。その最新版は2013年につくられた「IntCal13」。この「IntCal13」では水月湖の年縞のデータが高く評価され、最も信頼できるデータとして採用されているのだ。これが水月湖の年縞が「世界標準のものさし」と呼ばれるようになった所以だ
未知の細道の旅に出かけよう!
こんな旅プランはいかが?
年縞を知る!三方五湖と博物館を巡る旅
予算の目安 一泊二日:15000円〜
- 1日目
-
若狭町へ。まずは年縞博物館へ。水月湖の年縞の実物を見て、7万年をタイムトリップ。おとなりの若狭三方縄文博物館も合わせて見学してみよう。
宿泊は水月湖周辺などの湖側のほか、トンネルを隔ててすぐそばの海沿いにもたくさんある。周辺には温泉も。食事はもちろん日本海の魚介がオススメです! - 2日目
- レインボーラインで、三方五湖と日本海をドライブしよう。レインボーライン山頂公園からは三方五湖と若狭湾の絶景を堪能できる。カフェで鯖カツサンドなどのランチボックスを買ってケーブルカーに乗るのがオススメだ。
※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは
テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。
気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。
きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。












