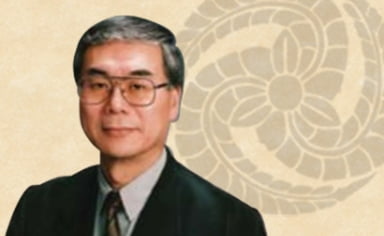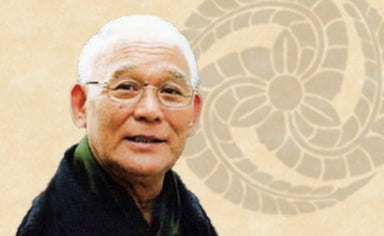- トップ
- 「鬼平江戸処」とは?
- 江戸の町並み再現
江戸の町並み再現
- 江戸の世界を、史実に基づいて忠実に再現 -

鬼平江戸処では、鬼平が生まれた1745年から、江戸びとが最もイキイキしていた文化文政までの江戸の世界を、史実に基づいて忠実に再現しています。時代考証は民俗学者の神崎宣武氏、空間デザインはアートディレクターの相羽高徳氏、音の風景は宮田章司師匠、全体の企画〜推進は総合プロデューサーの工藤忠継氏に依頼して、江戸の日常性を追求しました。
目の前に広がる江戸の町並み

車を降りると、まるで江戸びとが暮らしているかのような江戸の日常性が現れます。
目の前に、江戸の繁栄を象徴する日本橋の大店が立ち並び、一歩入るとそこは鬼平が闊歩した本所深川。
鳥のささやきの合間に物売りの声が聞こえ、美味しそうな匂いが漂い、朝から夕へと移り変わる空の色とともに、江戸の時間がゆったりと流れています。
わいわいがやがや、何やら楽しそうなものが見えてきたら、そこは江戸一番の賑わい処・両国広小路の屋台の連なり。
どれにしようかな・・・旅のひと休みに、楽しい時間をお過ごしください。
江戸の町並み再現
鬼平江戸処では、今ではあまり見ることのできない江戸の生活に欠かせないものが、たくさん散りばめられています。ここでは少しご紹介。ぜひ足を運んで探してみてください。

高札
高札とは、庶民に法令を告知するために板に筆で書いたもので、印刷技術や伝達手段の整備がされていなかった当時、橋の袂や人が多いところに、目立つように一段高くした「高札場」という場所が設置され、様々な高札が掲げられていました。
ここ鬼平江戸処では、人としての倫理を説いたものと、火付高札と呼ばれ、火付けは重罪に処する旨を定めた高札を掲げています。

半鐘
火事が多かった江戸の町では、町を見渡せる火の見櫓(やぐら)が各地に設けられ、火事を見つけると半鐘という鐘を鳴らして火事の発生を知らせ、火消しを集める役目をしていました。火消は屋根の上を走って火を消しに向かいます。建物の屋根の軒が揃っているのはそのためです。

打ち水が心地よいPA
緑に包まれた江戸はリサイクルの町でもありました。道具は壊れたら修理して何度も使い、着物は着古したら布巾にする。夏の夕方には一斉に打ち水をして、お隣さん同士で「今日もお疲れ様、明日も良い1日を・・」なんておしゃべりをしながら地面を冷やし、心を癒す。そんな心温まる毎日が繰り広げられていました。
江戸の樹木に囲まれて緑いっぱいのPA・鬼平江戸処では、足にも自然にもやさしいリサイクル材の地面を使用しており、打ち水効果による心地よさを作り出しています。
「鬼平犯科帳」の作中の風景を再現!

鬼平好きにはたまらない!「鬼平犯科帳」作中に登場するさまざまなシーンを再現しています。鬼平江戸処で楽しめる鬼平が闊歩した町並みをご紹介します。
鬼平江戸処の「オリジナル判じ物」
判じ物とは、言葉を別の文字や記号などに置き換えて読ませたもので、隠された意味を当てさせる言葉遊びを”判じ物” といいます。
“判ずる=推測して考える”という意味から、”判じ物”と言われています。
当時、謎かけを楽しむだけでなく、文字が読めない人への伝達手段としても親しまれていました。
問題
さあ、この判じ物はどんな意味でしょう

解説しましょう。
最初の図は斧です。斧は昔は「よき」とも呼ばれていました。
次の図は○に九を逆さにしたもの。○九→「まるく」を逆さにし、「クルマ」。
この九は鬼平江戸処の食と土産の9店舗も表しています。
最後の図は足袋「たび」です。
-
 ・・・よき
・・・よき
-
 ・・・くるま
・・・くるま
-
 ・・・たび
・・・たび
答え:良きクルマ旅
江戸で流行った遊び心“判じ物”に私たちの願いを込めました。安全なドライブの旅をお楽しみください。