

静かで落ち着く空間だ。

高山さんの作品。



「二階に上がってみませんか」
という声に誘われて、部屋の中心にあるスチール製の階段を上った。
そこは、いくつかに区切られた空間があった。中心にはやはりソファがあり、窓ぎわに本を読むのに良さそうな木のテーブルがある。この家にはいたる所にくつろぐ場所があるのだ。
低い壁で区切られた空間のひとつは、「お前ももう高校生だからなあ!」と三年前に作られた源樹君の部屋だ。その一角に、変わった木の椅子があった。
 「それ、僕が作ったんです」と源樹君が言うので、ちょっと驚いた。滑らかな木肌に曲線的なフォルムで、とても個性的だ。
「それ、僕が作ったんです」と源樹君が言うので、ちょっと驚いた。滑らかな木肌に曲線的なフォルムで、とても個性的だ。
「これは、わざと傾斜をつけて、足が組めないように設計したんです。僕、足を組む癖があるから、直したいと思って」
と、座ってみせてくれた。わざわざ足を組むと安定感を失うようにデザインされている。
「源樹くんも、なんでも作れちゃうんですね!」
それはごく当たり前かもしれない。なにしろ、彼は子どもの頃からこの家作りの主力メンバーだったのだ。幼い頃からコンクリートをかき混ぜたり、材木にかんなをかけたり。ペンキ塗りから家具作りまでなんでも手伝った。
そして、ここは益子である。周囲も、ものづくりをしている人ばかり。自分たちで家を建てている家族も何組もいた。そんな環境で育った彼は、自分のお小遣いをはたいて陶芸家の作品を買うような小学生になった。
彼が10歳の頃のこんなエピソードが残っている。カリフォルニアの陶芸家、アダム・シルヴァーマンが展覧会のために益子にやってきた。その溶岩のような質感の作品を見た源樹くんは、大興奮。
「益子では見たことのない釉薬!すげー! どうやって作ってるんですか!?」
とアダムに必死で話しかけた。
日本語を解さないアダムにも、その熱意と興奮はしっかりと伝わったようだ。彼は、「ちょっと待っててね」と、ひとつの器を少年に手渡した。それは、白と鮮やかなブルーの抹茶碗だった。そして、「大きくなったらLAに来なさい」と言った。
 源樹君がアダム・シルヴァーマンからもらった抹茶碗。
その後アダムは、大人気の陶器ブランド「ヒース・セラミックス」のスタジオ・ディレクターに就任。まさにアメリカを代表する陶芸家となった。
源樹君がアダム・シルヴァーマンからもらった抹茶碗。
その後アダムは、大人気の陶器ブランド「ヒース・セラミックス」のスタジオ・ディレクターに就任。まさにアメリカを代表する陶芸家となった。
源樹君が益子で開眼したのは、焼き物や家具だけではなかった。学校が終われば、釣りに出かけ、近所のお年寄りの農作業を手伝う毎日。喜んだ農家の人たちは、「これ持っていけ」と大根やネギをランドセルに突っ込んだという。そんな彼は地元の人の間で大人気になり、高山さんが歩いていると、「あ、源樹くんのお父さんですね!」と声をかけられたという。
さっきのアダム・シルヴァーマンの話には、後日談がある。
昨年の夏、カリフォルニアで、額賀章夫さんという陶芸家を中心とした展覧会が企画され、高山さんとガラス作家の杉山洋二さんが渡米した。その時、高山ファミリーは実に七年ぶりにアダムとの再会をとげた。源樹君を一目見たアダムは、「大きくなったなあ!本当に来たね!」と嬉しそうに微笑んだそうだ。
そうか、そうか、と私は納得した。高山夫婦はこつこつと家を作りながら、もうひとつの作品も育てた。それは、息子という一人の人間である。
今18歳になった青年は、イタリアに行く準備をしている。一年かけて農業や食、ワインなどに触れて来る予定だ。
「高校2年の時に初めて一人でイタリアに行ったんです。その後アメリカにも行って、どちらもすごく楽しかったけどアメリカから帰ってきた時に、少し疲れた気がして。でも、イタリアから戻った後は逆にすごく元気だったなあ。なんでかなあ、と思った時に、それは食のせいなのかなって。だからイタリアに行ってきます」
そんな感受性豊かな源樹君に、夫婦は「ここにきた意味がありますよね」と頷いた。
こんなユニークな家族の暮しを支えているのは、やはり益子という町が持つ独特のカルチャーだろう。しかし、それは一朝一夕にできあがったものではないそうだ。
「ここには、古くから都会と田舎、そして世界と日本が融合する独特のカルチャーがあったんです」
と高山さんは話してくれた。
 高山英樹さん。二階の眺めの良い窓ぎわで。
彼によれば、益子の歴史には、三人の外からきた革命児がいた。一人目は、人間国宝の濱田庄司である。
高山英樹さん。二階の眺めの良い窓ぎわで。
彼によれば、益子の歴史には、三人の外からきた革命児がいた。一人目は、人間国宝の濱田庄司である。
大正14年に益子に移り住んできた彼こそが、まさに益子焼きの立役者だ。
「益子って、実は焼き物の里としては後発で、歴史が浅いんです。濱田庄司が移り住んできて、周囲に声をかけて、濱田窯ができた。最初は、外から来た濱田さんは、『なんだ、あいつ』と思われていたんじゃないかな。でも濱田さんは偉かった!自分が作ったプロトタイプを公開して、みんなにコピーを許した。それが俗に言う今の益子焼スタイルになったんです。」
そして、高山さんは「益子にきたら、一度はあそこに行かないと!」と、私たちを車に乗せてエンジンをかけた。数分で街中に入ると、立派な日本家屋の前に到着。それは、「益子参考館」。濱田庄司の自邸とアトリエを利用した美術館である。
立派な門をくぐると、花が咲き乱れる気持ちの良い庭が現れ、立派な日本家屋や蔵がいくつも点在している。
建物の中には、中南米やアジア、ヨーロッパから集めた無数の民芸品や木工品が並んでいる。私たちも良く知るイームズチェアやルーシー・リーの器もある。それは、世界を旅した濱田が、こつこつと集めた逸品。参考館という変わった施設名は、「他の人にも参考にしてもらいたい」というものばかりを展示しているから。アトリエの奥の方には、「登り窯」という数メートルの大きさの窯もあった。これで、何百という焼き物を一遍に焼いたそうだ。
濱田庄司が益子にきたのは、ちょうど関東大震災の頃だ。当時、東京では大量に器が必要になり、東京に近かった益子は、どんどん器を出荷。そして、ひとつの全盛期を迎えた。それが、第一次の益子革命だったという。
「二人目のキーマンは、60年代の陶芸家、加守田章二だった」と高山さんは言う。加守田の作品は、かなり自由だ。波打つような形や曲線に彩られ、生命感が溢れだす。「アバンギャルド」を体現する作品は、陶芸界に衝撃を与え、数々の賞を受賞。加守田に憧れた人たちが続々と益子に移り住み、益子焼に新たなムーブメントを呼び起こした。
「そんな経緯があるから、益子の地元の人も、移住してきた人に優しいんです。外からきた人は、いい形で町を変えてくれると思っているんですね」
そして、三人目のキーマンが、スターネットを作った馬場浩史さんである。
益子参考館を後にして、スターネットまで足をのばすことにした。
 スターネットへ。今はその知名度は全国区。
ここを建てた馬場浩史さんもまた、東京でファッションやデザインなどに関わり、益子に移り住んだ一人だ。
スターネットへ。今はその知名度は全国区。
ここを建てた馬場浩史さんもまた、東京でファッションやデザインなどに関わり、益子に移り住んだ一人だ。
「スターネットができた頃から、益子が面白くなってきた。ここを巣立った人たちがカフェやパン屋さんを始めたりして、どんどん町が変化してきた」
高山さんは、益子に越してくる時にひとつのイメージを持っていた。それは、「ここがバリ島のウブドみたいになったらいいな」ということ。
ウブドかあ。言われてみれば、ここはどことなくウブドっぽい。田園風景があって、芸術家がいて、漂うセンスがどことなく都会的で。
「でも、当時の益子は、今の益子とは全然違いました。おしゃれなカフェやショップもほとんどなかった。でも、カフェがなかったら自分たちで作ればいいと思ったんですよ」
そうやって、仲間と力を合わせて、町を育てていこう。時間さえかければ、どんなものでも自分たちで作れるんだから―—。それは、家づくりと、同じ発想だったのだろう。
今や益子は、移住者と地元の人がほどよくミックスされ、「風景は田舎だけど、カルチャーは都会」という独特の風土ができあがった。歩いてみれば、田んぼがあり、野菜市場があり、居心地の良いカフェがあり、古道具屋があり、ギャラリーがある。ひとつひとつは独立したものではなく、すべて有機的につながり、町の生態系を形づくる。
もちろん、高山さんの家もその生態系の一部だ。
そういう有機的なつながりを表現した場所が、このスターネットなのだろう。
ショップには、陶器を中心としながらも、農作物やパン、着心地の良い洋服や、使いやすい日用品が並べられている。高山さんが作ったどっしりとした古材の棚は、そういうものを静かに引き立てていた。
私たちはショップでクッキーを買い込んだあと、スターネットのカフェでお茶を飲んだ。人気のカフェは混んでいたが、案内されたのは、偶然にも高山さんが作ったテーブルの席だった。
すべすべとした木のテーブルに美味しいコーヒー。幸福な雑談。人生、これ以上何もいらない、というような瞬間だ。
こんな感じなので、人には「次は(家を)どうする予定ですか」と高山ファミリーはしょっちゅう聞かれる(確かに気になる!)。
「てきとうに『外壁とお風呂』とか言うんだけど、すぐ別にやりたいことがでてきちゃうんだよね。最近は、家の隣にギャラリーを作ったし」(高山さん)
ああ、あれか、と家の隣の青い木枠の建物を思い出す。あれ、でもちょっと待って。「さっきお風呂っていいました?」と私は聞き直した。
「そう、お風呂はまだ五右衛門風呂です」
「ええ!じゃあ、薪で湧かすんですか」
「そう!でも最近はホーローのいいのがあるんですよ。夕飯を食べる前に薪に火をつけておけば、30分くらいで沸きますから~」
加えて、暖かい日は自家製の太陽温水器(工費2万円!)でお湯が作れるので、薪は必要ないそうだ。
ということで、あまり不便は感じていないらしい。
「だから、いつもお風呂は後回し!」(源樹君)
まさにあの家は、ネバーエンディングなのである。
そして一方の益子では、2009年から3年に一度の土祭(ひじさい)という芸術祭が始まり、高山さんは初回から参加している。
「それは、益子を底辺から構成しているものを再確認することで、暮しを表現できないかという試みでした」
益子の自然、文化、土壌のすべてを見せることで、「田舎での幸せな暮し」を表現する。総合プロデューサーは、スターネットの馬場さん。
第二回目では神社の境内に、「たてものの未来 食卓の家」という作品を作った。それは、電気やガスを使わない食堂を表現する。見た目は、まるで縄文時代の竪穴式住居のよう。中にはぐるりと石が並び、車座に座るようにできている。それはきっと、古き良き昔を懐古しようという話ではない。無駄なエネルギーを使わないでみんなで囲む食卓は、実は人類が目指す未来の食卓そのものなのだろう。
 第二回目土祭の出品作品。「たてものの未来 食卓の家」
そして、馬場さんは昨年、残念ながらこの世を去った。それでも土祭は続いていくだろうし、いつしか益子はまた新たな変革者を迎えるのかもしれない。
第二回目土祭の出品作品。「たてものの未来 食卓の家」
そして、馬場さんは昨年、残念ながらこの世を去った。それでも土祭は続いていくだろうし、いつしか益子はまた新たな変革者を迎えるのかもしれない。
高山さんは、益子で家を建て、作品を生み出し、家族を育てた。そして、益子という町も、高山家を育ててくれた。いや、その言い方は正しくない。ここは一つの生態系なんだ、と思い出した。ここにいる全員、そしてここに生きるもの全てが相互に作用して、未来へと進化し続ける。
なんだか、すごいじゃないかと思いながら、美味しいコーヒーをまた一口飲んだ。

- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。
テーマは「名人」「伝説」「祭」の3つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。
未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。
(毎月2回、10日・20日頃更新予定) 
-
-
update | 2014.5.27
美しき未完成の家へようこそ! 木工作家とその家族、あるいは益子の物語[後編]
- starnet スターネット
- 陶器を中心に農作物やパン、着心地の良い洋服や、使いやすい日用品など。
〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子3278-1
0285-72-9661
starnet スターネット - 益子参考館
- 公益財団法人 濱田庄司記念益子参考館
〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子3388
Tel/Fax 0285-72-5300
益子参考館

川内 有緒 ノンフィクション作家
日本大学芸術学部卒、ジョージタウン大学にて修士号を取得。
コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。
その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。
2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。
書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。
著書に、パリで働く日本人の追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』他。
『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)で第33回新田次郎文学賞を受賞。
![美しき未完成の家へようこそ! 木工作家とその家族、あるいは益子の物語[前編]](images/title.png)
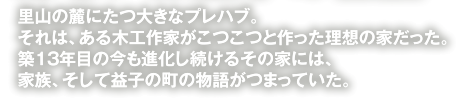
![美しき未完成の家へようこそ! 木工作家とその家族、あるいは益子の物語[前編]へ](images/zenpenhe.png)
