






青空が広がっているのに、細かい雪がフワフワと舞っていた。この辺ではよくある天気なんですよ、地元商店の女性が教えてくれた。
「山の方ではきっとたくさん雪が降っているんでしょうねえ」
そんな大寒波が到来する中、私は宮城県の鹽竈神社(しおがまじんじゃ)を訪れていた。江戸時代から伝わる数枚の「絵馬」を見るためである。
東京から新幹線で仙台へ、そして東北本線に乗りかえる。
いったいどんな物だろう、と列車に揺られながら想像していた。なにせ鹽竈神社のHPにも特に何も触れられていなかった。
塩釜駅から歩くこと数分、石の鳥居の奥に、長い参道が現れた。
「わあ、ここかあ・・・」と思わず空を見上げた。
本格的に降り始めた雪の中、お年寄りが足を引きずるようにして参道を登っていた。私も一歩ずつゆっくりと登り始めた。ユーモラスな表情の狛犬が優しく見送ってくれる。
絵馬と表現したが、そこには馬の絵も、願いごとも書かれていない。代わりにあるのは、数学の問題だけだ。
えっ、神社に数学?と思うだろう。私も最初に聞いた時は、そうだった。
数学の問題が書かれた絵馬は「算額」と呼ばれ、今も日本全国に千ほどが残っている。
とはいえ、今私たちが使っている数学とはちょっと違う。江戸時代の日本は鎖国政策のおかげで、数学すらもガラパゴス化。まったく独自の進化をたどっていた。そういう日本独自の数学は、「和算」と呼ばれている。
千以上もある算額の中でも、鹽竈神社のものは特別な存在だ。問題は和算の最難関で、いくつかは奉納から178年を経た現在でも解答法が発見されていない “未解決問題”なのだ。
そう聞くと、どこかエジプトのピラミッドをほうふつとさせる。いったい、誰がなんのためにそんな難問を作ったのだろう。
数学は大嫌いな私だが、とかく歴史ミステリーには目がないのだ。
息を弾ませながら参道を登りきると、まだお正月のムードを残した境内には、たくさんの人がお参りに来ていた。正面の拝殿の屋根が、銅色にキラキラと輝いている。しばし見とれてしまった。
「ちょうど屋根を葺き替えたばかりなんです。ここは式年遷宮があるんですよ。二十年に一回、屋根を吹き替えています」
と神社職員の方が教えてくれる。この神社の起源は非常に古く、奈良時代以前までさかのぼる。長い間、陸奥国(むつのくに)一之宮として、大名や武士、そして庶民の尊敬を集めた。
![]() 張り出されていた遷宮の奉賛者名に目が止まった。リストの筆頭には伊達家十八代当主の名前が。もちろん、あの伊達政宗の子孫である。
張り出されていた遷宮の奉賛者名に目が止まった。リストの筆頭には伊達家十八代当主の名前が。もちろん、あの伊達政宗の子孫である。
「すごいですね」
と思わず感心の声を上げた。この地には、日本史の教科書でしか見ないような血脈が確かに残っているらしい。
境内には、大勢の人が描いた絵馬がずらりとぶら下がっていた。合格祈願に家内安全といった定番のお願いの他にも「K君とラッブラブになりたい!」「嵐ライブが当たりますように」なんていうのもある。さらに進むと、「献魚台」と書かれた看板があった。
![]() ―えっ、魚?
―えっ、魚?
「そうです、マグロの漁師さんたちが航海安全でよく魚を奉納にきますよ。ここの御祭神の鹽土老翁神(しおつちのおじのかみ)は、漁業の守り神でもあるんです。ほら、あそこに海が見えるでしょう」
と指差した先には、確かに遠くに海が見えた。
嵐のチケットにマグロ。人々は、思い思いのお願いや奉げ物を胸にここにやってくる。
そう、時には数学の問題まで。

さて問題の「算額」は、神社の博物館の中にあるらしい。
博物館に入ると、すぐに目に飛び込んできたのは、立派なおみこし。奥には現代刀の特別展が続く。二階は塩をテーマにした展示物がずらり。ゆっくりとめぐるが、お目当ての「算額」は見つからない。
そういえば、どれくらいのサイズなのだろう。絵馬というくらいだから、小さいに違いない。改めて見直すが、それらしきものはない。受付で聞いてみようかな、と思ったその瞬間。
あ、待てよ、あれかも……!
学校の黒板ほどの巨大な板が、階段脇のスペースに掲げられていた。あわてて近づくと、円や三角形などのたくさんの図形。そして筆でびっしりと書かれた文章。図形も文字も墨が薄くなっている。
これだ!
私は近寄って、読んでみようとした。しかし、「今有三角内如・・・」などと漢文で書かれているので残念ながらチンプンカンプン。うーむ。
算額の端に、かすかに「千葉」「一門」という文字が見えた。
神社職員の方に、算額がここに納められた経緯を聞いてみた。
「記録によれば、天保七年(1836年)に千葉胤秀(たねひで)の一門が奉納しにきて、当神社の志賀が受け取ったようです。志賀は当神社の神主の家柄の一人です」
1836年といえば、もう江戸末期で、幕末の動乱が始まる直前だ。そんな時期に問題を奉納にきた千葉胤秀という人は、いったいどんな人物だったのか。
「農民の出身だったらしいです」
「そうなんですか?農民が数学を?」
「ええ、3000人の弟子がいたそうで、この地方を代表する和算家です。ただ、残念ながらこの算額が奉納された時の詳しいやり取りは記録に残っていないんです」
それにしても、どうしてこの神社を選んだのだろう。
「きっと陸奥国一之宮で、大きな神社だったからでしょうね。ただ(神社の)大小に関わらず、色々な神社に算額が納められているそうで、当時はとにかく問題が解けたことに感謝して、さかんに神社仏閣に奉納したようですから」
それにしても不思議だ。
世界広しといえども、数学の問題を神様に捧げるなんて、聞いたことがない。
学業成就までは、理解できる。私も高校受験の前は、学業の神様・湯島天神に行ったものだ。しかし、私がお願いしたのはあくまで「合格」だ。とうぜん、「神様、見てください。私、こんな難しい問題を思いつきました!」と絵馬に書いたりはしなかった。
しかし、どうやら江戸時代は、それが普通だったらしい。
どうにも理解しがたい風習に首をひねりながら、いくつか本や資料を紐解いてみた。そして、愕然とした。
数学を奉納する理由……その答えはなんと、大好きだから!
そう、江戸時代の庶民は、とにかく数学が大好きだった。
かように、当時の若者の会話を現代風に再現すると、こんな感じになる。
「ねえ、この問題知ってる?」
「きゃー、難しそう!やってみたい!」
「僕は、もうクリアしたから貸してあげるよ」
「え、いいの?じゃあ、写本して返すね!」
当時の数学は今でいうゲームやパズルみたいなもので、息抜きや娯楽だった。ほら、私たちも小学校のときに習った旅人算とか鶴亀算。ああいう問題を人々はヒマを見つけては解いていたらしい。
しかし、なにゆえに神社に?
それを知るために、もう少しだけ江戸時代を旅してみたい。
話はそれるようだが、江戸時代には一冊の大ベストセラーがあった。それは、1627年に出版された『塵劫記(じんこうき)』。著者は、和算家の吉田光由である。
その本は、和の単位や九九、計算の方法などをイラスト入りで解説。「一冊で日常必要な算術をすべてカバー!」という充実ぶりで、売れに売れまくった。もっと深く数学を知りたい!という熱烈なファンも出現し、巷には数学塾が次々と設立された。
しかし、ベストセラー作家の吉田にとっては、派手なブームは頭痛の種でもあった。世の中には、塵劫記に続け!とばかりに海賊本が溢れた(どこの世界も一緒ですね)。しかも、一部の海賊版のレベルは低いときてる。
困った吉田は、「これが本物です」と立派な改訂版を出した。しかし、二匹目のドジョウ狙いは後を絶たない。そこで吉田は、必殺技を繰り出した。「遺題」という挑戦状を巻末につけたのだ。
「にわか和算家たちよ。これを解いて実力を示しなさい」
というのがメッセージなので解答はつけない。
ちょっとしたアイディアの「遺題」は、予想を超えた熱狂を巻き起こした。他の和算家達も新たな問題を作り、著書に載せ始めたのだ。一つの遺題が次の遺題につながり、「遺題継承」というリレー現象に発展。リレーは170年も続き、問題はどんどん高度化していった。
もうひとつブームが、例の「算額奉納」である。たくさんの人が集まる神社仏閣を発表の場に見立て、難問を奉納する和算家達が現れた。「挑戦してみなさい」というわけだ。これは和算家の実力を示す役割もあったのだろう。今ならインターネットのポータルサイトに投稿するようなものかもしれない。人々は家や道場に問題を持ち帰り、解答ができたらまた奉納にくるという習慣が繰り返された。
そうやって生まれ出た難問が、この鹽竈算額なのだ。
きっと千葉一問は知恵を絞って最高の問題を考え、満を持して奉納に来た。三メートル以上もある巨大な板に書いたことからも、その気合いが伺える。
神社職員の方は、当時の様子をこう説明してくれた。
「かつての鹽竈神社には『絵馬殿』という場所があり、人々が絵馬を奉納しに来ていました。この算額も絵馬殿にあったようです。普通の絵馬はお炊き上げをしますので残っていないのですが、これは個人の願意を表すものではなかったのでお炊き上げされなかったのでしょう」
その後、算額は幕末の動乱にも世界大戦にも耐え抜いた。しかし長い間に損傷が進み、いたずら書きがされている部分もあったらしい。戦後になって、ようやく今の博物館に収められた。
ああ、貴重な算額が残っていて良かったなあ、と改めてほっとする。実際に歴史の中で失われてしまった算額も多数あるらしい。
それにしても、この博物館の中においては、算額はどちらかといえばマイナーな展示物の印象だ。もう今や、和算に興味を持つ人は多くはないのかもしれない(この日も、算額を見学しているのは私だけだった)。
なにせ明治維新以降は西洋の数学が入ってきて、和算は教育の本流から姿を消した。そして、日本人は和算の解き方もあらかた忘れてしまい、今やその存在すら知らない若者も多い。
そして後に残されたのは難問のみ。誰にも解かれないままに。
ところが2011年、止まっていた時計の針が動き出した。
「和算研究会の全国大会が宮城県で行われた際に、この算額を見たいという話があり、特別公開したのです」
和算研究会とは、その名の通り和算の研究や普及を目的とする団体で、日本各地に支部がある。年に一度全国大会では、和算の縁の地を見学して歩く。そしてその年に選ばれたのが、鹽竈神社だった。
熱心な申し入れに心を動かされた神社は、普段は公開していない算額も含めて特別に公開。そして会員達は、算額の67題のうち18題が、“未解決”であることを改めて知り、奮い立った。
この問題を解かなければ!
そして、11人のメンバーが全問解明に向かって立ち上がった。
実はこの後、その会の一人に会う約束をしていた。
この博物館の前で。
180年の難問に挑め!塩釜神社の「算額」に残された江戸時代の挑戦状[後半]に続く

- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。
テーマは「名人」「伝説」「祭」の3つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。
未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。
(毎月2回、10日・20日頃更新予定) 
-
-
update | 2014.2.10
180年の難問に挑め!塩釜神社の「算額」に残された江戸時代の挑戦状
- 志波彦神社・鹽竈神社
-
古くから東北鎮護・陸奥国一之宮として、朝廷を始め庶民の崇敬を集めて今日に至る。
平成14年12月、本殿・拝殿・四足門(唐門)・廻廊・随神門以下計14棟と、石鳥居1基が、国の重要文化財の指定を受けた。
【観光についてのお問い合わせ】
〒985-8510 宮城県塩竈市一森山1-1
志波彦神社・鹽竈神社

川内 有緒 ノンフィクション作家
日本大学芸術学部卒、ジョージタウン大学にて修士号を取得。
コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。
その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。
2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。
書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。
著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。
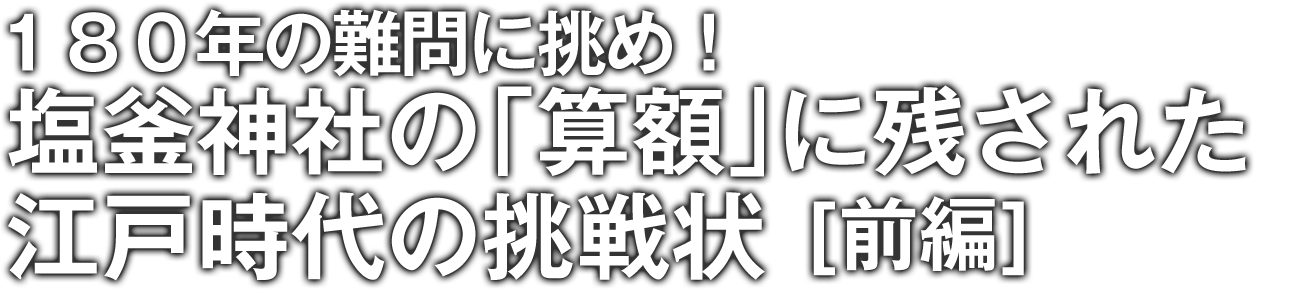

![180年の難問に挑め!塩釜神社の「算額」に残された江戸時代の挑戦状[後編]へ](images/kouhenhe.png)
