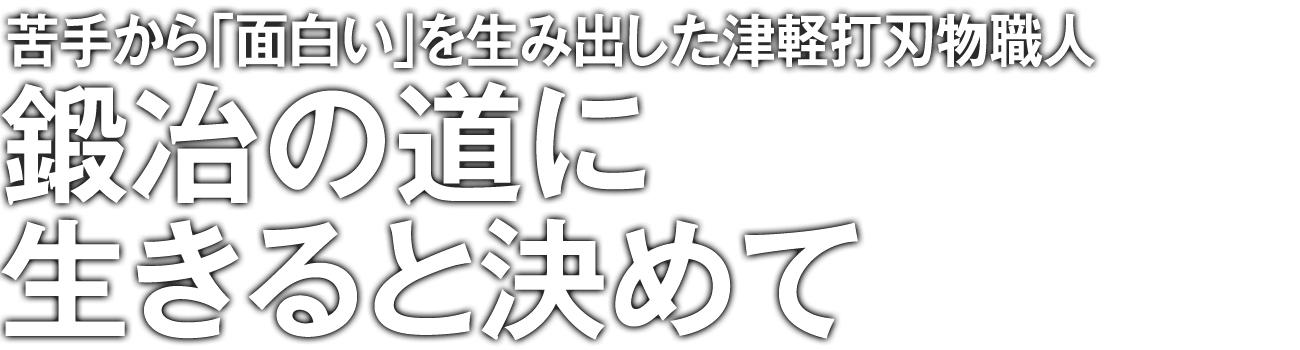中では社員の方々が真剣に作業に打ち込んでいた。

このようにメモしておくんです」
と吉澤さん

「譲りたい」といって刀が集まってくるという。
その一部を見せてくれた。


これは広大な敷地の一部に過ぎない。


未知の細道
15- 名人
- 伝説
- 祭り


「新しいことに挑戦し続けている職人さんがいる」
弘前市の職員から折り返しの電話があったのは、雨の降る夜のことだった。
面白い職人を知らないか、との無茶な問い合わせに応じ、候補となる人物を見つけてくれたのだ。傘をさしながら東京の路上を歩いていた私は、慌ててメモを取り出しその名前を書きとめた。
「吉澤俊寿(よしざわ としひさ)」
二唐刃物鍛造所(にがらはものたんぞうじょ)の社長で、「津軽打刃物」の鍛冶職人だという。
パリの「メゾン・エ・オブジェ」というインテリア・デザイン国際見本市に出展したり、ドイツで開催された「Ambiente 2013」という世界最大級の消費財の見本市でも展示を行ったりと、伝統的な製法を守りながらも、国際進出にも積極的にうって出ている人物だそうだ。
「ありがとうございました!調べてみます」
さっそく、メモした名前を検索エンジンに入力してみる。
出てきたのは、青森県卓越技能者受賞や弘前マイスター認定などの華々しい経歴。しかし、記事の中の彼のある発言に、思わず目を奪われた。
「もともと不器用な人間で、ものづくりは苦手なほうでした。でも、売る現場に出てお客さんの生の声を聞くようになってから、面白いと感じるようになったんです」
「頑張ってものづくりをしたら、ポルシェにだって乗れるし、大きな家だって建てられる」
「売る現場」での体験が、職人の仕事を楽しくするのも不思議だったし、ものづくりとポルシェもどうにもうまく繋がらなかった。それに、彼の人生を変えてしまった「お客さんの生の声」って一体どんな声だったのだろう。
ネット上をいくら調べても出てこないそれらの真相に、がぜん興味がわいてきた。
―よし、彼に会いに行こう!
私が、「津軽海峡冬景色」を口ずさみながら上野発の夜行バスに乗り込んだのは、その3日後のことだった。

「ロックが好きで長髪で、いわゆるビートルズ世代の若者でした」
そう笑う吉澤さんの笑顔は、55歳とは思えないほどのパワーとエネルギーを発散していた。
「職人気質(しょくにんかたぎ)」という言葉があるように、職人といえば、ひたすら技を極め、ものづくりに徹する頑固一徹な人物を想像しがちだ。しかし、彼のまとう空気は、そのイメージとはまったくかけ離れたものだった。
私が彼のもとへ訪れたのは、まだ雪の残る3月上旬のある日のこと。
弘前駅前から金属団地行きのバスに乗り込み25分。
「南高校前」で下車するとすぐに、「カーン、カーン」という金属のぶつかる音が風にのって聞こえてきた。
音を頼りに閑散とした住宅街を進むと、工場地帯らしい一角に突きあたる。
二唐刃物鍛造所は、刃物だけでなく鉄構事業も手掛けている。広大な敷地だが、おそらくここに違いない。事務所らしき建物のチャイムを鳴らすと、作業着姿の吉澤さんが「どうぞどうぞ!」と出迎えてくれた。
耳にかかる長さのロマンスグレーの髪に、ややオーバーリアクションな所作、くしゃっと笑う愛嬌のある笑顔が、日本の中年男性というよりは、イタリアやフランスの陽気な紳士を思わせた。
案内されたのは「自分でデザインしたんです」という、鍛造の技術を使って作られた応接セット。見ればテーブルやいすの足部分に鉄が使われている。こんなものまで作ってるんですか!と話も盛り上がり、取材は和気あいあいとスタートした。
そもそもの話になるが、どうしてものづくりの苦手な吉澤さんが、鍛冶職人になったのか。
その理由を語るには、少しだけ時代をさかのぼらなければならない。
弘前には、「さくらまつり」で有名な弘前城がある。
江戸時代初期、その城下町として栄えた弘前市内には、桶屋町、大工町、馬屋町、紺屋町など、当時の町並みに由来する地名が今も残る。そのうちのひとつに「鍛冶町(かじまち)」があり、その名の通り最盛期には100軒以上もの鍛冶屋がその地に軒をつらねたという。
「二唐刃物鍛造所」の元祖二唐家がのれんを掲げたのも、そんな弘前の地であった。
二唐家に代々伝えられてきた作刀技術は、昭和の名匠・五代目「二唐国俊(にがらくにとし)」の数々の受賞により、広く世に認められることとなる。
そして、この二唐国俊の長女が、吉澤さんの母。つまり吉澤さんは二唐国俊の孫というわけだ。叔父にあたる国次氏が六代目を務めるも、後継ぎがいなかったため、甥であった彼に次のスポットがあてられた。
「中学2年生になると、夏休みとか冬休みに祖父の仕事の手伝いに行かされるようになりました」
ものづくりの基本を学ぶため、高校は弘前工業高校の機械科に進学。大学も、親に言われるまま八戸工業大学の機械工学科に進学したという。
「決められたレールを迷わずに行くような、素直な子だったと思います」
いまや刀鍛冶の一時代を築く鍛造所の社長が、この道に進むことになった理由……、
なんとそれは「親に言われたから」だったのだ。
「でも、ものづくりは苦手だったんですよね?」
気になって尋ねてみると、
「そうなんですよ」
吉澤さんからは、間をおかずに答えが返ってきた。
「高校や大学でもある程度理屈っぽい部分は勉強していたんですけど、実際に作るってことはないわけです。実習も限られたものしかありませんし……。で、手がものすごく不器用。もともと私は『作る』ってこと自体が非常に苦手なタイプでしたから」
22歳で弟子入りすると、案の定、刃物づくりに悪戦苦闘した。
兄弟子からは、こんな言葉で批判されることもあったという。
「津軽の郷土料理に『じゃっぱ汁』ってあるんですよ。鱈の『あら』……要は、食べることのできないところですね、これでだしをとって、大根とかを煮つける料理なんですけど。
津軽弁で『じゃっぱ』っていうのは、『使い物にならないもの』のことを言うんです。
でね、兄弟子が、私の作った包丁を見て言うわけですよ、『じゃっぱ』って。『そんなじゃっぱ捨てろ』って」
ひとたび製品に「二唐」というマークが入れば、誰が作っても二唐刃物鍛造所の商品になる。だからこそ一定の質を超えたものでないと、単なる「じゃっぱ」でしかない……そんな意味もこめられていたのだと、吉澤さんは言う。
「入りたての頃に言われたのは、『百本包丁を作ったら百本全部切れないとだめ』ということです。さらに言えば、包丁を使う人の中には、家庭の主婦もいれば、鮨屋の板前さんもいますよね。そういった全ての利用者に共通する『切れる』を追求すると、かなり高いレベルが求められるんです」
不器用な彼に、その言葉は相当な重さを持ってのしかかったに違いない。
「この世界入ってから、『やっぱり合わないからやめよう』と思ったこともありました。そしたら、おふくろから『お前がやめたら、自分は実家に出入りできなくなる』と泣き落しされまして。私も、素直ちゅうか単純なんでしょうね、それで、もうちょっと頑張ってみるか……となって」
そんな彼に人生の転機が訪れたのは、25歳の時だ。
青森県の物産展に出展するため、東京の玉川高島屋に一週間だけ出向く機会があった。季節は6月末の暑くなる時期。彼は、ラフな服装の上にエプロンを身につけて刃物の販売に挑んだ。
売り場の課長から「同じデパート内に、『本物』の刃物職人がいる」という話を聞いたのは、そのときのこと。天下の高島屋の課長が言う「本物」とはどんな人なのだろう―。吉澤さんは物産の合間をぬって、その「本物」とやらを見に行ってみることにした。
向かったのは、家庭用品売り場の催事コーナー。
普段は自分の店で営業している職人だが、その期間中だけデパートに売りに来ているのだという。
そこにいたのは、「職人」そのものといったいでたちの男だった。
きれいに刈り上げた髪、白の和装肌着に、膝下までの紺のパッチ(神輿担ぎを連想させるスタイル)…そして、周囲にはたくさんの人だかりができていた。
「お客さん、これ見て!」
男は、目の前に置かれた砥石に、包丁の刃先を「トントン!」と叩きつけてみせた。
「ね、かけないでしょ」再び刃先をお客さんに見せると一言「これ硬いからね」。
客のひとりが包丁を買おうとすると、「ちょっと待ってね」と新聞紙を取り出す。
手に持った包丁をスッと新聞にあてると、パッ!っと切れる。それを見た周囲の客からは「わぁぁっ!!!」という驚嘆の声が漏れる。
そうして男は、たった今切ったばかりの新聞に丁寧に包丁をくるんでお客さんに渡すのだ。
「今でもその光景ははっきりと覚えてます。衝撃でした」
吉澤さんが見た男の正体は、東京・亀戸に店を構える「吉實(よしざね)」の、吉澤操氏(名字が同じなのは偶然だそう)。職人としての腕前も一流だが、実演販売の腕前も一流の人物だった。
「次の日さっそく箱菓子を持って行って、ヨシザネさんに教えを乞いました」
―これが現場の生の声なんだ。ただいいものを売っているだけじゃお客さんは買ってくれない。『売り方』を変えていかなきゃいけなかったんだ……!
そんな想いが、吉澤さんの中をいっぱいに満たしていた。

吉澤さんの申し入れに対するヨシザネさんの返事は、「よし、帰りに寄るから」。
「雅号を入れたのれんを作ったらいいとか、包丁の使い方を書いたプラカードを飾るとか、並べ方はこうすると綺麗に見える、とかそんなことを教えてもらいましたね」
それから彼は、徹底的にヨシザネさんの真似をした。
夏だったので、浴衣の売っているコーナーに行き、まずは甚平を手に入れた。草履と、カーキ色のズボンも入手した。スポーツショップに行って、ヘアバンドまで買ったという。
「やっぱり人って、まずは外見で判断するじゃないですか。だからまぁ、軽いかもしれないけども、見た目から真似をしたんですね」
吉澤さんが、仕事を面白いと感じ始めたのはその時からだった。
―ものづくりの先には、人がいる。
買ってもらうために、何を工夫したらいいだろう、次にできることはあるだろうか。
気付けば、原点であるものづくりの仕事にも、以前に増して熱が入るようになっていた。
それからは、物産に出る度に、吉澤さんはデパート中を見て回ったという。
「刃物を作ってるから刃物だけを見る、という発想になりがちですが、そうすると視野が非常に狭くなるんです。とにかく、なんでも見ておけばいろんなものが頭に蓄積される、そうすると、ふっとデザインが浮かんだり、アイデアが湧いてきたりするんです」
私は思わず大きくうなずいていた。それは、どんな職業にも通じる話だと思う。
もの書きだってそう。できるだけいろいろなものを見聞きして体験したほうが、文章に深みが出るというものだ。まさか、ひとつの道に打ち込み極める職人さんの口からそんな言葉が聞けるとは思っていなかった。
「で、やっぱりね、私たちがこうやって少しでも生き延びているのは『オリジナルを作れるから』だと思ってます。自分たちでデザインして、自分たちで作りますんで」
「学ぶ」と「真似ぶ」は同じ語源だという説もあるが、まさしく彼は、真似から入ってオリジナルを生み続けてきたといっていいだろう。
腰かけた応接セットの椅子とテーブルが、なんだか誇らしげに見えた。

事務所には、応接セットの他にも、鍛造技術を使って作られたであろう様々なものが飾られていた。
そのひとつが、刃物で作られたオブジェ。
良く見ると表面には、無数の波紋のような模様が広がっている。
「その模様はね、『暗紋(あんもん)』ていいます。鋼を重ねて、何度も何度も繰り返し叩くことによってこういった美しい模様ができあがるんですよ」

刃物で作られたオブジェ。
表面には鋼を幾重にも重ねて打ちつけたときに
できる模様「暗紋」が浮かび上がる
この「暗紋」は、平成19年に始まった商工会議所のプロジェクトの一環で生み出されたという。それは、津軽打刃物職人の活動を支援する、大がかりなプロジェクトだった。
「その年も、すごく忙しかったんです。でも自分は動き出した船には乗るタイプだったんで、だめだったら降りればいいと思って乗りました。人生の大きい波ってそうそう来ないですから」
だめだったら降りればいい―まさしくこの覚悟が、吉澤さんを新たなチャレンジへと突き進めてきた原動力のひとつなのかもしれない。
実際、ヨシザネさんのスタイルを取り入れるようになってから、仕事は軌道にのったかのように思えた。しかし、結婚をし子供を持つ身になると、年間に何十週もまわらなければいけない催事への参加は過酷を極めた。その上、宿泊費や人件費などを考慮すると、よほどの数を売らない限り採算が合わない。
吉澤さんはこの時、ここまで自分を乗せてきてくれた小舟を思い切って降りることにした。
「やっぱり地元で、飯を食えるようなスタイルを確立しないと」
新しい刃物製品を開発するにもお金がかかる。当時38歳、会社の跡取りとしてすでに専務の職に就いていた吉澤さんは、まずは財政の立て直しを!と、利益率の高い鉄講事業の再建に着手したのだ。
「商売で物を売ることを覚えてたので、新しいお客さんを新規開拓することにしたんです」
そうして吉澤さんが始めたのは飛び込みの営業。鉄骨屋の飛び込み営業なんてほぼありえないことで、先代の社長には「そんなとこ行ったってお前、相手にされないよ」と笑われたという。
「いやいや、その頃に飛び込んだお客さんとは、今も付き合いが続いてますよ」
やってだめだったらそれでいい。やらないで諦めるのが一番くだらないことです、と吉澤さんは言った。
新たな船に乗り換え、知恵を絞って荒波や悪天候に立ち向かった吉澤さんは、どこに到着したのか。その現在地こそが、今の「二唐刃物鍛造所」だ。今では安定した経営環境の中、長男・剛さんが経営にかかわったり、技術を受け継ぐ職人が育ったりと、今後の発展につながる新たな芽も出始めている。後継者不足の鍛冶屋業界であるにも関わらず、だ。
冒頭で紹介したパリの「メゾン・エ・オブジェ」も、「暗紋」を制作したプロジェクトの流れで行くことになったのだという。そこで高い評価を得ることができ、それがさらにドイツの国際展示会出展につながった。
多忙な中でのプロジェクト参加となったが、結果的には、そういった国際進出や新たな技術の誕生により注文も増えたそうだ。
「吉澤さんは常に考えて、新たなことに挑戦してきたんですね」
彼は、持ち前の明るい笑顔を見せて答えた。
「そうですね、なんか窮地になればなるほど、『ブァッ!』と力が湧くタイプなんです」
さて、肝心の「不器用さ」はどうなったのか。
その答えは、取材のあとに連れていってもらった鍛冶場で明らかとなる。
煤色の工場内。
ここより先に進まないようにという吉澤さんの言いつけにしたがい、少し離れた場所からカメラをかまえる。
炉の横の窪みにスタンバイすると、彼の目つきが一気に真剣になった。

炎があかあかと燃える炉の中に、おもむろに鉄の塊を差し込む。
高温の炎に熱されて真っ赤になった鉄を取り出すと、
まずは金槌をつかって整え、それから専用の機械で何度も叩く……。
鉄がだんだんに冷めてくると再び炉に戻し、また真っ赤になったら取り出して叩く。
そんな作業がなんども繰り返され、最初はただの鉄の塊だったものが、あっという間に「包丁」の形になっていた。
それはまさに「職人技」といった様相を呈していて、私はただただあぜんとするしかなかった。飛び散る火花が美しく、たちあがる煙が幻想的だった。
「私は不器用な人間でしたけど、だからこそ、諦めずに何度もチャレンジすることができたんです」
不器用だったからこそ、「作る」だけではない、様々なチャレンジを続けることができた。
不器用だったからこそ、苦手なものづくりにすぐに満足せず追求することができた。
吉澤さんから溢れるパワーとエネルギーの正体は、そんな「逆境力」だったのかもしれない。
相変わらずの大きな笑顔を浮かべて、彼は言った。
「ここまでこれたのも、『自分はこの仕事で生活していくんだ!』って想いが根底にあったからだと思います。大切なのはまず、『これで飯食うんだ』って意識を持つことなんですよ」

- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。
テーマは「名人」「伝説」「祭」の3つ。
様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。
未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。
(毎月2回、10日・20日頃更新予定) 
-
-
update | 2014.4.21
苦手から「面白い」を生み出した津軽打刃物職人 鍛冶の道に生きると決めて
- 有限会社二唐刃物鍛造所
-
青森県弘前市の国交省認定工場。350年続く津軽の刀鍛冶の伝統と技を活かし、品質の高い製品を製造している。
[TEL] 0172-88-2881 [WEB] 二唐刃物鍛造所
- 青森県弘前市
-
青森県の最高峰、岩木山の東側に位置する。
津軽名物のリンゴの畑、弘前ねぷたまつり、津軽三味線大会、国の重要文化財でもある弘前城での弘前さくらまつりなど、自然と伝統を楽しむことができる町。
【観光についてのお問い合わせ】
弘前市 観光政策課 [TEL] 0172-35-1128 [WEB] 弘前市役所ホームページ 観光TOP
弘前観光コンベンション協会 [TEL] 0172-35-3131 [WEB] 弘前観光コンベンション協会 - 弘前さくらまつり
-
日本一の桜と称される桜と弘前城を共に楽しむことができ、毎年多くの観光客で賑わう。
[WEB] 弘前さくらまつり

ライター 坂口直
1985年、東京都生まれ。
大学卒業後、海外特許取得に係る手続きの代理業に5年間従事。
初めてアジア以外の海外を訪問した際、異文化の面白さを感じ、まだ見ぬ人や文化に出会いたいという思いが芽生えるようになる。
その思いを遂げるべく、2013年春よりフリーのライターとして活動開始。現在はWeb媒体を中心に活動を広げている。